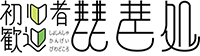琵琶あれこれ
こちらのページではよりニッチに展開。今現在日本で演奏されている各琵琶の違いや、創作琵琶の詳細などを載せていきます。

琵琶ギャラリー
現在、日本に存在していて演奏されている琵琶は楽琵琶・平家琵琶・薩摩琵琶・筑前琵琶です。
それぞれの演奏方法というのではく、各琵琶の形や大きさはどう違うのか?
(PC版だと4種類並べて見れます)この「形」になった時期は、
楽琵琶が奈良時代、平家琵琶が1200年代終わり〈平家物語の成立は1302年頃とされていますので〉
薩摩琵琶が180年代の終わり。筑前琵琶が1900年代の初頭と思われます。
どれも記録が残っていないので推測でしか書けないのが残念です。
琵琶クローズアップ
日本で最も弾かれているのは薩摩琵琶と筑前琵琶。
それぞれの音色の違いは楽器の作りの違い。
その『琵琶の音色らしさ』を出すのは『フレット=柱』
『柱』の違いをじっくりご覧ください。
(画像をクリックすると拡大画像が出ます)
左側が薩摩琵琶、右側が筑前琵琶
薩摩琵琶の柱は硬い木が使われています。弾いていく内に柱の表面が削れて低くなってしまうので、
柱の下に下駄を入れて高さを調整して、常に柱の高さが変わらないようにメンテナンスします。
筑前琵琶の柱には板状のものが載っていますがこれは煤竹。こちらも弾いていく内に削れてきてしまうので、定期的に煤竹を張り替えるメンテナンスをします。
改良琵琶
演奏家には演奏旅行はつきもの。
その際、困るのは琵琶の運搬です。
丸ごと収納するケースを用意することもさることながら、海外では琵琶の装飾部品である象牙はワシントン条約に抵触する危険があり、そのための申請も一苦労。
それらをクリアする琵琶がこの改良琵琶。装飾部分は象牙の代わりに白蝶貝等を使い、、、なんと!分解できてしまうのです。その手順をギャラリー形式でご紹介。
(画像をクリックすると拡大画像が出ます)
-

こちらがその改良琵琶 -

まず、糸を外します。 -

糸巻きから外して… -

半月付近でまとめます